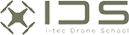ドローンの語源
「Drone」という言葉は、英語でオスのミツバチを意味します。飛行時のプロペラの音がミツバチの羽音に似ていることから名付けられたとする説や、第2次世界大戦前にイギリス軍で訓練用に軍人達が射撃していた、無人で飛行する「クイーン・ビー(女王バチ)」から転じて呼ばれるようになった説など、由来・語源は諸説あります。また、ドローンの類義語としては「無人航空機」(日本の航空法)、「UAV(unmanned aerial vehicle)」(英:頭文字から)「UAS(unmanned aircraft systems」(米連邦航空局)等があります。
無人航空機
飛行機、回転翼航空機(ドローン)、滑空機、飛行船の構造上人が乗る事の出来ないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので、これらの100g以上(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものをいいます。
模型航空機
無人航空機の重量が100g未満(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものをいいます。一見、模型航空機は様々な規制の対象外と思われている方もいらっしゃいますが、「小型無人機等飛行禁止法」や航空法の一部においては規制の対象となりますので注意が必要です。
ドローンの法規制について
無人航空機には航空法が適用されます。
国内のドローン産業の普及とともに法整備も進んでおり、2023年4月時点の情報ですが、大きく分けて「飛ばす場所に関する規制」、「飛ばす方法に関する規制」、「機体の登録に関する規制」、「資格(国家ライセンス)に関する規制」、やその他共通で、電波法や道路交通法、海岸法、河川法、民法、個人情報保護法、自治体の条例など守らなければいけないルールがいくつかあるので、正しい理解と知識で安全にドローンを利用することが重要です。
ドローンの種類・用途について
種類としてはホビー用のトイドローンや産業用ドローン、水中ドローン、軍事用ドローン等があります。最近ではニュース等でも話題になっている「空飛ぶ車」等も総じてドローンという括りの中にあります。
用途としては、上空からの撮影業の分野、農薬散布などの農業分野、測量計測やインフラ設備の点検、物流など多様な分野でドローンが活用されております。今後も法整備等が進んでいく中、様々な分野でドローンを活用した新たなビジネスが今後も期待されます。産業用以外では、趣味での空撮用やレース用のドローン等もあります。
※ドローンのプロポ(送信機)にはモード1~4がありますが、モード2が主流となっています。
ドローンの国家資格について
ドローンの資格については、民間のスクールが発行する民間資格に加えて、2022年12月5日より国家資格制度(無人航空機操縦者技能証明)が開始されました。
資格制度が設けられてから、解禁された一部の飛行(カテゴリーⅢ、レベル4)を除いては、現在、必ずしも無人航空機操縦者技能証明の取得は必要ではありません。
但し、国家資格を取得する事により、一部条件はありますが飛行申請等の簡素化や免除等のメリットはあります。また、今後拡大が予測されるドローンビジネス市場への参入を検討、もしくはこれから更に事業拡大を計画される方にとっては、確かな操縦技術や法規制を正しく理解したドローンオペレーターの確保や対外的な信頼線の担保として、国家資格の取得推進は大きなメリットがあると考えています。